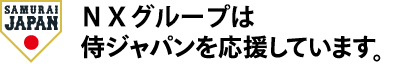プロも緊張「震えていた」 元北海道日本ハム・田中幸雄氏が振り返るシドニーの戦い
日本代表の五輪挑戦には長い歴史がある。当初はアマチュア選手で構成され、公開競技だった1984年ロサンゼルス大会で金メダルを獲得した。続く1988年ソウル大会で銀メダルに終わると、正式種目となった1992年バルセロナ大会では銅メダル、1996年アトランタ大会では銀メダルと金から遠ざかった。そこで2000年シドニー大会を迎えるにあたり選んだ道は、プロ選手の力を借りること。「侍ジャパン」の名前もなかった時代に、8人のプロがシーズン中にも関わらずチームを離れ、日本野球のプライドを掛けた戦いに臨んだ。

写真提供=Full-Count
初めてプロが参加したシドニーで日本代表チームに最年長で選出
日本代表の五輪挑戦には長い歴史がある。当初はアマチュア選手で構成され、公開競技だった1984年ロサンゼルス大会で金メダルを獲得した。続く1988年ソウル大会で銀メダルに終わると、正式種目となった1992年バルセロナ大会では銅メダル、1996年アトランタ大会では銀メダルと金から遠ざかった。そこで2000年シドニー大会を迎えるにあたり選んだ道は、プロ選手の力を借りること。「侍ジャパン」の名前もなかった時代に、8人のプロがシーズン中にも関わらずチームを離れ、日本野球のプライドを掛けた戦いに臨んだ。
日本ハム(現・北海道日本ハム)で遊撃を守り、クリーンアップを打っていた田中幸雄氏は当時32歳。チーム最年長としてその一員に名を連ねた。韓国との3位決定戦に敗れ、惜しくもメダルを逃した戦いを振り返れば、今でも悔しさがこみ上げる。
「メダルですか……。そりゃあ、欲しかったですよ。誰に見せるわけでもないでしょうけどね」。一方で、いい経験だったという思いもある。「1回しか出てないし、それも21年も前の話ですよ。でも、今でもこうして話を聞きたいと言ってもらえる。出たことが、引退した後も財産になっているのかもしれませんね」。
出場に興味はなかった。というよりも、縁のないものだと思っていた。「アマチュア選手でやるものだと思っていたから、なぜ自分が選ばれたのかわからなかった」と明かす。「行きたくないな……」というのが、選出を聞いた当時の正直な思い。ただ知人に相談すると、誰もが「こんな機会はない。行ったほうがいい」と背中を押してくれた。金メダル挑戦が持つ影響力の大きさを知った。
新人時代のようなプレッシャーに「打席で震えてました…」
シドニーの野球競技は9月17日からスタート。シーズンへの影響を最小限にとどめるため、プロ選手はぎりぎりまで公式戦をこなした。田中氏も9月13日まで出場を続けてから代表に合流。現地入りしてからチームを作っていくような状態だった。「初めての経験でしたからね。プロではベテランかもしれませんけど、どうしたらいいのか……」と思案。そこで、3度目の出場だった杉浦正則投手(日本生命)に「年は俺が一番上だけど、遠慮なくまとめ役をやってほしい」と伝えた。
日本は前年に韓国・ソウルで予選を戦い、本戦への出場権をつかんでいた。田中氏はその中にはいなかったものの「韓国とは互角だろう。あとは米国、キューバはどうか」と各国の力関係を読んでいた。初戦の相手は、その一角でもある米国。グラウンドに立つと異変は起きた。
「緊張しましたし、負けられないというプレッシャーは本当にありました。打席で震えてましたからね。そんなの、プロに入ったばかりの時以来ですよ」
実は左手首に故障を抱えており、シドニーでも病院で見てもらうような状態だった。慢性的な肘の痛みもあった。そんな中でもプロとして結果を求められる。ポジションをつかもうともがいた、若き日のように心は締め付けられた。
日本は初戦を延長13回に及ぶ激闘の末、2-4で落とした。予選リーグは4勝3敗で、田中氏がライバルと見ていた3チームには勝つことができなかった。
キューバとの準決勝を前に選手が音頭を取り、改めてミーティングを持った。野手は「点を取らないといけない」と口を揃え、当時ロッテ(現・千葉ロッテ)の黒木知宏投手や西武(現・埼玉西武)の松坂大輔投手は「逃げずにインコースを攻めていこう」と意思統一を図った。腕の長い外国人選手を抑えるには、失投のリスクがあっても内角を攻めなければならない。それでも、白星は遠かった。0-3で敗れ、3位決定戦に回る。
遠かったメダル…やり返す場のない大きな喪失感
9月27日、韓国との3位決定戦は、翌年オリックス入りする具臺晟投手(当時ハンファ)に抑え込まれた。9回に田中氏は1-3と追い上げる適時打を放ったがそこまで。悲願の金どころか、メダルをつかめずに終わった。「その瞬間は『負けちゃった……』と、呆然としてましたね。何人かは泣いてました。とにかく次がないので落ち込みましたね」。長いペナントレースと違い、もうやり返す場がなかった。負けで終わった時の喪失感は、あまりにも大きかった。
現地の球場では日本人のファンから『日本に帰れると思うなよ』と罵声も浴びた。プロ選手が初めて参加した歴史の転換点は、決して成功とは言えなかった。個人成績は日本が戦った全9試合のうち8試合に出場し、打率.323、2本塁打。7打点は中村紀洋内野手(近鉄)に次ぐチーム2位と立派なもの。それでも「プロとして期待されていたのに、日本国民の期待に応えられなかった」。充実感は皆無だった。
勝つためには何でもやった。チームを盛り上げるために申し合わせたガッツポーズがあった。胸を突き出し、両手を肩の高さで引く姿だ。元来、控えめな性格の田中氏は「照れはありましたよ。でもそんなこと言ってられませんからね」と、率先してポーズをとった。そしてこのポーズが誤解を招き、オランダの選手が激昂する場面もあった。あらゆる常識の違いがぶつかり合う舞台だった。
「野球はずっとやってほしいですし、やらないなんてあり得ないと思っています」
その後もアテネ大会、北京大会と続いた野球競技は、今回の東京までの2大会では行われなかった。復活の一報を聞いた時は胸が高鳴った。
「野球はずっとやってほしいですし、やらないなんてあり得ないと思っています。盛んでない国があるのも分かりますけど」
次回、2024年パリ大会では採用されなかったが、2028年の米国・ロサンゼルス、2032年の豪州・ブリスベンと野球人気が高い国が続く。もし再度復活することがあるならば、太い腕のスラッガーは、1人でも多くの後輩たちに心がひりつくような経験をしてほしいと願っている。
記事提供=Full-Count
写真提供=Full-Count