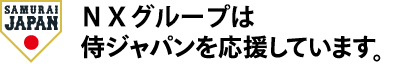第1、2回WBC戦士・福留孝介が振り返る連覇の軌跡 肌で感じた米国の本気度の変化
「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™」(以下WBC)(2026年3月5〜17日)の開催まで、ついに半年を切った。井端弘和監督率いる野球日本代表「侍ジャパン」は、11月の「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」、そして3月の強化試合を経て、2度目の連覇をかけた戦いに挑む。

写真提供=Getty Images
2006年の第1回大会では準決勝で痛烈な代打ホームラン
「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™」(以下WBC)(2026年3月5〜17日)の開催まで、ついに半年を切った。井端弘和監督率いる野球日本代表「侍ジャパン」は、11月の「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」、そして3月の強化試合を経て、2度目の連覇をかけた戦いに挑む。
日本が1度目の連覇を果たしたのは、2006年と2009年の第1、2回大会だった。この時、主力メンバーとして貢献した1人が、日米球界で通算24年プレーした福留孝介氏だ。第1回大会では、準決勝の韓国戦で鮮烈な代打先制2ランを放ったことは、今でも語り草となっている。あの興奮から20年が経とうとする今、福留氏に当時を振り返ってもらった。
当時のMLBコミッショナー、バド・セリグ氏が音頭を取り、新たな“野球世界一決定戦”として産声を上げたWBC。だが、当初は何もかもが手探りで、実際にはどんな大会になるのか、何を期待していいのか、想像することが難しかった。
「日本の選手たちは『新しい世界大会が始まるんだ。頑張ろう』という思いはあったと思います。ただ、米国やドミニカ共和国といった他の参加国がどこまで真剣なのか、その温度感がまったく分からない状態でのスタートでした。日本はそれなりに盛り上がっていたけれど、客観的に見ると、大会そのものよりも、王貞治監督の下、メジャーでバリバリ活躍するイチローさんが日本代表のユニホームを着て戦うことに対する盛り上がりの方が強かったんじゃないかと思います。福岡での事前合宿の時も、ファンの方々の注目点はそこでしたよね」
日本と米国で感じたWBCに対する温度差
東京ドームでの1次ラウンドは韓国に敗れたものの、2勝1敗の2位で通過。日本は意気揚々と2次ラウンド以降の舞台となる米国へと向かった。だが、いざ米国に到着してみると、MLB球団と練習試合を行ったアリゾナでも、2次ラウンドが開催されたアナハイムでも、いまひとつ盛り上がりが伝わってこない。他チームが怪我を理由に次々とロースターを入れ替える様子からも「オープン戦の延長くらいの感覚なんだろう」と感じていたという。
さらには、米国がまさかの2次ラウンド敗退。決勝トーナメントに進んだのが、日本、韓国、キューバ、ドミニカ共和国の4チームだったこともあり、現地で盛り上がっていたのはアジア系とラテン系住民が中心だった。その中でも異様な熱気を帯びたのが、日本と韓国が火花を散らした準決勝だ。
日本は予選ラウンドで韓国に2連敗。加えて、2次ラウンドでの敗戦後にはマウンドに韓国の国旗を立てられる出来事も起きた。その直後、珍しく怒りを露わにするイチロー氏の姿が話題となったが、福留氏も「あれからが始まり、のようなところはあったと思います」と話す。
準決勝が開催されたドジャースタジアムでは日系住民と韓国系住民が応援合戦を繰り広げ、スコアボードには「0」が並ぶ。緊張の糸がピンと張り詰める中、均衡を破ったのが福留氏の目が覚めるような代打2ランだった。日本は3度目の正直で韓国に勝利し、決勝では乱打戦の末にキューバを撃破。初代王者として帰国の途に就いた。
日本に戻ると、待っていたのは大フィーバーだった。「凄かった!」「感動した!」と声を掛けられ、嬉しく思うと同時に、改めて日本と米国の温度差を実感したという。「優勝はもちろんだけど、2敗した韓国に3度目は勝った。日本の盛り上がりはそこが強かったんじゃないですかね」と振り返る。

普段は慣れない控えの役割も「ベテランの方々が率先して買って出てくれた」
福留氏にとって、この優勝は新たな気付きや学びを得る機会にもなった。そもそも、2005年11月にWBC出場を打診された際、打撃フォーム改造に着手していたこともあり、1度は出場を辞退していた。だが、12月に主軸と期待された松井秀喜氏が正式に出場を辞退すると、再び福留氏のもとに打診が届く。「2度も誘っていただいたので(出場することにした)。ただ、結果が出ない可能性は高いだろうという覚悟はありました」。
今でこそ日本代表もチーム内での役割を考えた編成が主流だが、当時は各チームの主力選手が集結。打線は全員が4番を打てる豪華さだった。福留氏は予選ラウンドでは正中堅手として全戦に先発し、主に3番打者を任された。その一方で「普段は控えに回ることのない人たちが、裏方の役割まで請け負って支えてくれた。その姿に刺激を受けました」という。
「代表チームは人数が限られているので、チームに必要な裏方の役割を選手が補わなければならない。そういう時、谷繁(元信)さんや宮本(慎也)さんといったベテランの方々が率先して打撃投手を買って出たり、自分の結果云々ではなく、見えない部分でチームを支えてくださった。日本ではなかなか見られない、そういう姿が有難かったし、僕にとっては大きかったですね。だから、この時の優勝はチームを支えてくれた方々への思いも含め、勝ててよかったという達成感がありました」
2008年にカブスへ移籍… 米国内で感じた本気度の変化
福留氏はその後、2008年にシカゴ・カブスへ移籍し、米国を本拠地とした。メジャー選手として1シーズン戦い終えて迎えた2009年の第2回大会。米国内でのWBCに対する温度感が、第1回大会とは明らかに変わったことを肌で感じていた。
「米国はWBC開催を主導したのに、前回は予選ラウンドで敗退してしまった。『それはちょっとないだろう』と本気度を上げ、第2回は早くからチーム編成にも力を入れてきたのが伝わってきました。同時に、主催者側も前回の反省を踏まえたルール整備をしたり出場チームを増やしたり、『長く続くしっかりした大会にするんだ』という思いが見えてきた。実際に米国にいたからこそ感じられた変化っていうのは、興味深かったですね」
原辰徳監督が率いるチームは、投手陣はダルビッシュ有投手、田中将大投手ら若い世代に一新されたが、野手陣はWBC経験者が多く揃った。監督も替わり、選手も替わり、前回優勝時とはまったくカラーの違うチームとなったが、日本国内からは連覇を期待する声が寄せられ、他の出場チームからは連覇阻止のプレッシャーがかかる。難しい状況に置かれながらも、日本は準決勝で米国、そして決勝では韓国に勝利し、2連覇を達成した。
「嬉しいというよりもホッとした感じ。『あぁ良かった。勝てた』という思いが強かったですね。投手陣は若手中心になっていたし、年齢が上のメンバーは特にやりきった感じがあったように思います。この先は若い選手にバトンを渡そう、みたいなところが」
24年という長いキャリアの中で、WBCに関わった時間はほんの僅かかもしれない。だが、WBCで味わった2度の世界一は何物にも代え難い経験となり、力強い光りを放ちながら福留氏の野球人生を彩っている。
記事提供=Full-Count
写真提供=Getty Images